ブログBlog

ブログ Blog
唾液は何のためにある?
歯科治療について
2025/08/28

こんにちは!
門戸厄神近くにある中津浜デンタルクリニック・
今日は私たちの口の中に、
【健康の鍵は口の中に?】
唾液の驚くべき役割とは?
私たちが日常生活で何気なく飲み込んでいる「唾液(だえき)」。
この記事では、「唾液の役割」
「食べる」「話す」「
⸻
⚫️まず唾液とは何でしょうか?
唾液は、主に3つの大きな唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下腺)と、
健康な成人であれば、
唾液の約99%は水分ですが、残りの1%
その1%
・ 酵素(アミラーゼなど)
・抗菌物質(リゾチーム、ラクトフェリン)
• 電解質(ナトリウム、カリウムなど)
・ 免疫グロブリン(IgA)
• ムチン(粘液成分)
これらの成分が相互に作用しながら、
⚫️唾液があるとこんないいこと
ここからは、
① 自浄作用(洗浄作用)
唾液は、食後に残った食べかすや糖分を洗い流してくれます。
特に流動性の高い「耳下腺唾液」がこの働きを担っており、
② 緩衝作用(中和作用)
私たちが食事をすると、口の中は酸性に傾きます。
ここで活躍するのが唾液の「緩衝能」です。
これにより、再石灰化(
③ 抗菌・免疫作用
唾液には、以下のような抗菌・免疫成分が含まれています。
• リゾチーム:細菌の細胞壁を分解
• ラクトフェリン:細菌の増殖を抑制
• IgA(免疫グロブリンA):病原菌の付着を防止
これらの成分により、口腔内の細菌バランスが保たれ、
④ 潤滑・粘膜保護作用
唾液に含まれるムチン(粘液成分)は、
⑤ 再石灰化作用
食事や飲み物によって歯の表面が一時的に脱灰されると、
⑥ 味覚や嚥下の補助
唾液は、味覚を正常に感じるためにも重要です。
唾液が少なくなると、「
⑦ 話す、歌う、表情を作る
唾液は、
また、声を出すときも、
つまり、
⑧身体全体の健康を守る
唾液の働きは、口の中だけにとどまりません。 唾液によって口腔内の炎症や傷が治りやすくなり、
口は「体の入り口」
特に高齢者では、
⚫️唾液の分泌が減るとどうなる?
唾液の量が減少する状態を「ドライマウス(口腔乾燥症)」
唾液が少なくなると、以下のようなトラブルが増加します
• 虫歯や歯周病の進行
• 口臭の悪化
• 入れ歯の不適合や痛み
• 話しにくさ、飲み込みづらさ
• 味覚障害、口内炎の発生
口腔環境の悪化は全身の健康にも影響するため、
⚫️唾液を増やすためにできることはなに?
日常生活の中で、唾液の分泌を促進する方法を取り入れることで、
①よく噛む
噛むことで唾液腺が刺激され、唾液の分泌が促されます。
②こまめな水分補給
脱水は唾液の分泌を妨げます。口が乾く前に、
③唾液腺マッサージ
耳下腺、顎下腺、舌下腺を指で優しくマッサージすると、
④舌・口周りの運動
「パ・タ・カ・ラ体操」などで、
⑤お口の清潔を保つ
プラークや細菌が多いと唾液の質が低下します。
⸻
【まとめ】
唾液は“天然の歯医者さん”
唾液は、私たちの口腔環境を守るために欠かせない存在です。
唾液の働きを意識して、
中津浜デンタルクリニック・こども矯正歯科は、
安心してお任せ下さい。
あなたへのおすすめ記事
-
-

- 歯科治療について
- 小児矯正はいつから始めるべき? ~後悔しないためのタイミングと考え方~
-
-
-

- 歯科治療について
- 赤ちゃんから始めよう!歯と骨の健康を守るフッ素
-
-
-
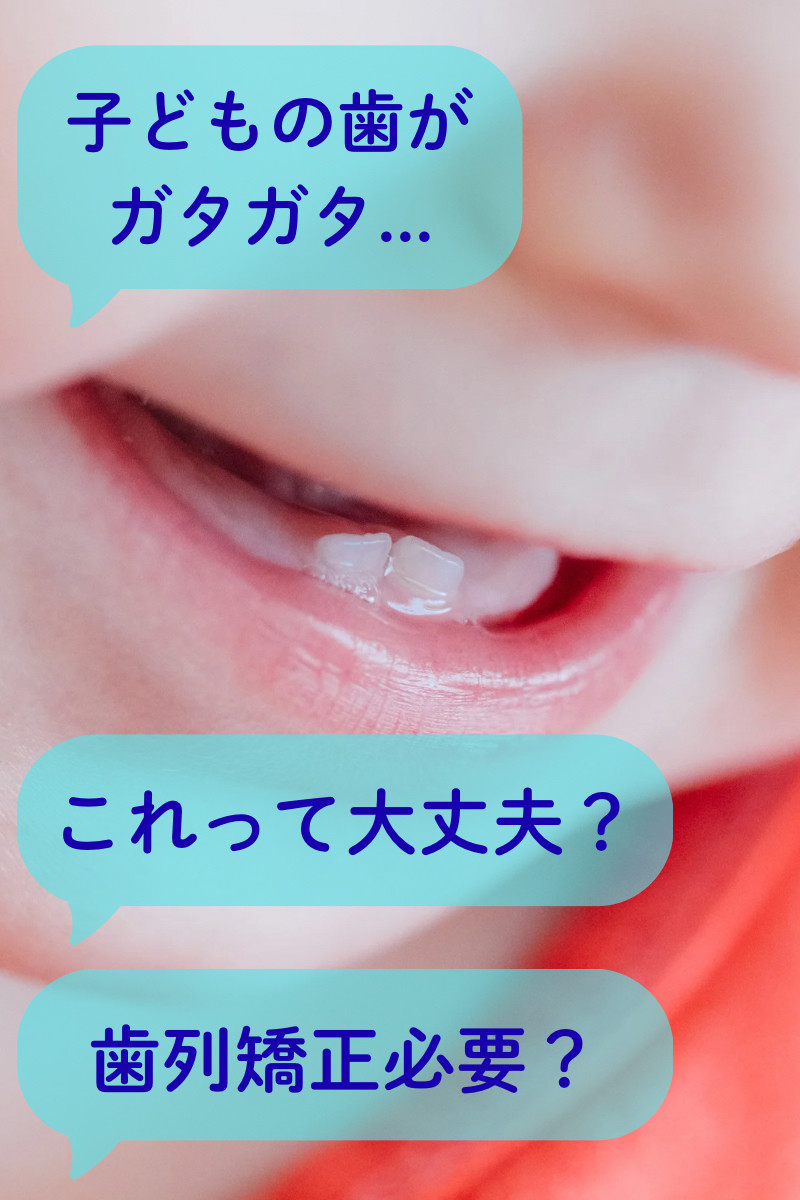
- 歯科治療について
- 子どもの歯がガタガタ…これって大丈夫?矯正は必要?と不安な親御さんへ
-
 電話する
電話する WEB予約
WEB予約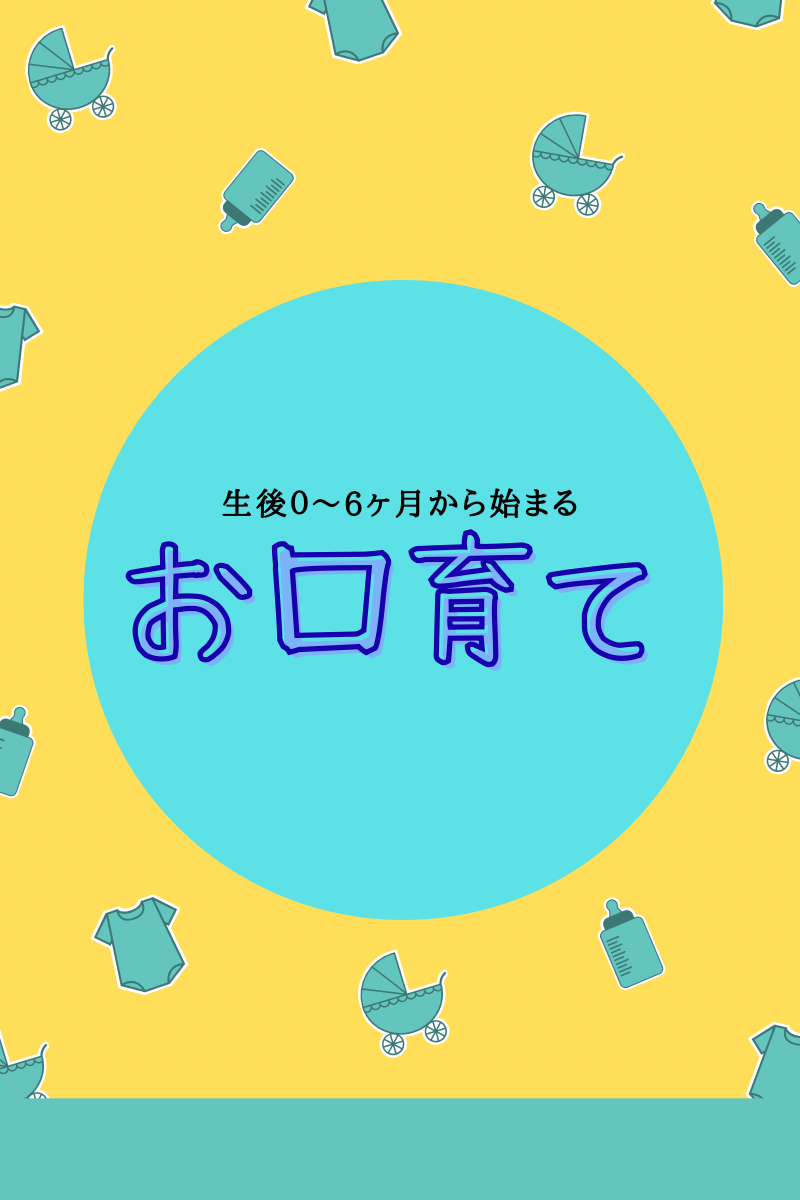
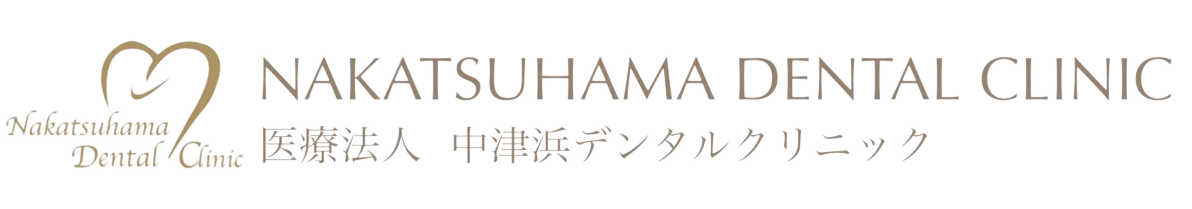

 0798-65-5611
0798-65-5611
